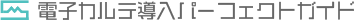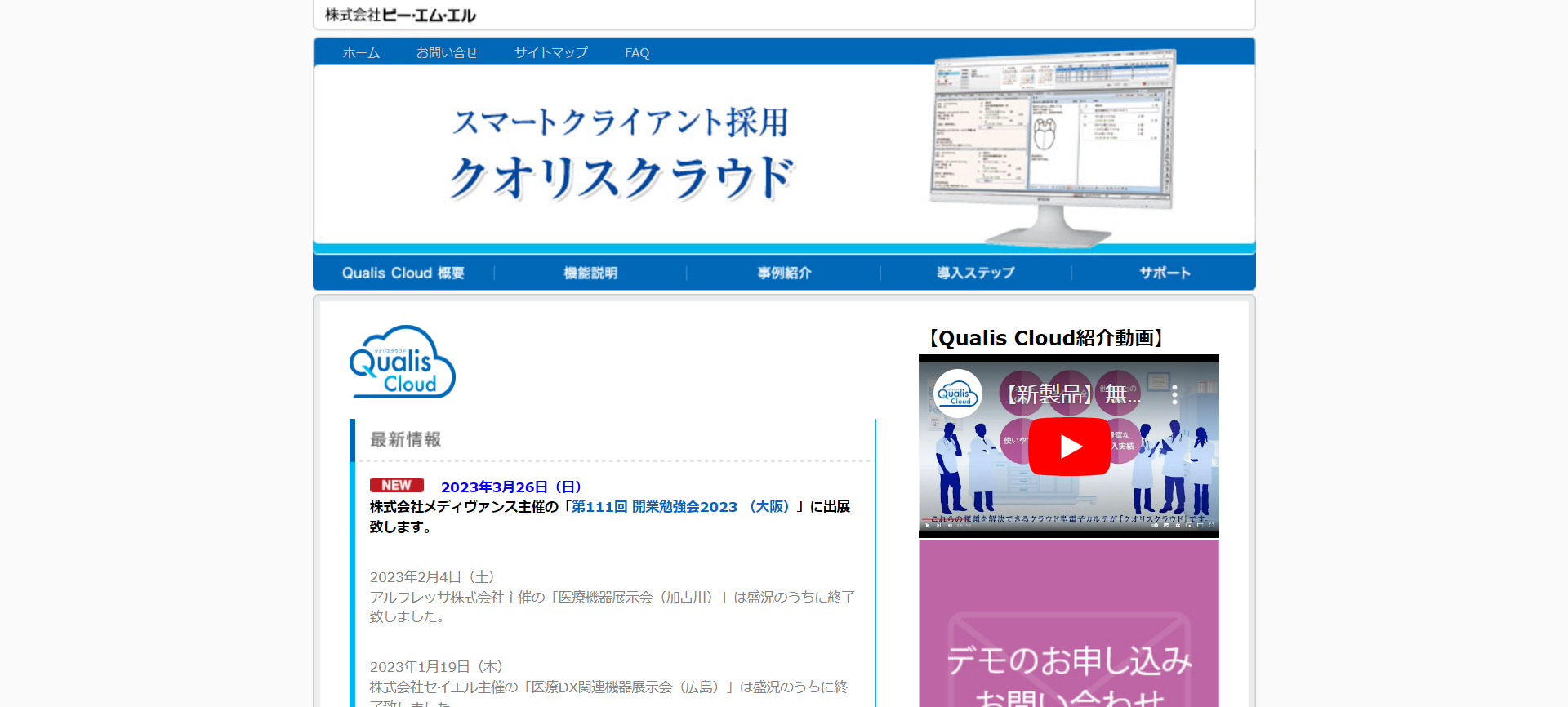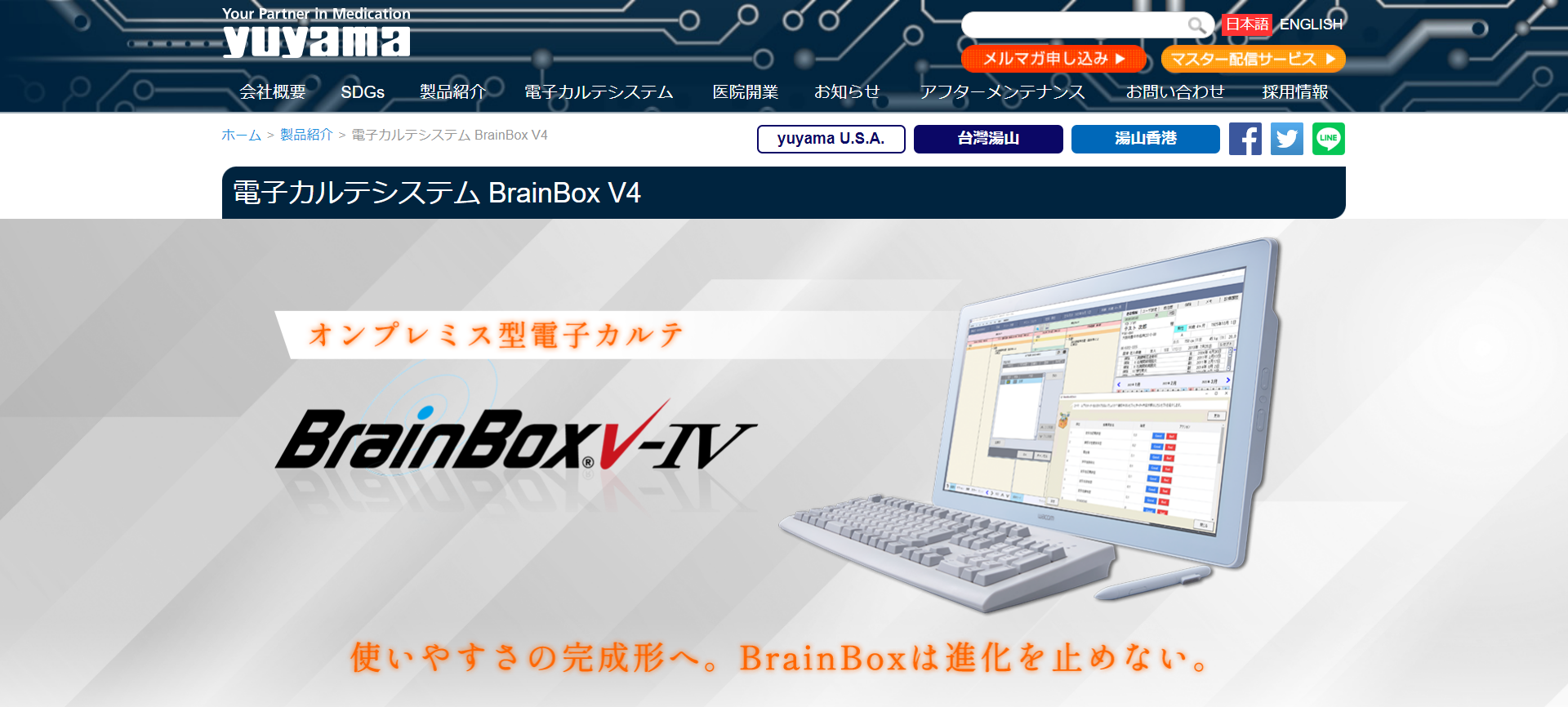医療情報取得加算とは?電子カルテでの対応方法を解説
ここでは、現代の医療現場において重要な役割を果たす電子カルテと、診療報酬改定に伴い改正された医療情報取得加算の仕組み、運用上の注意点について解説いたします。
電子カルテの重要性とその役割
電子カルテは、診療記録や検査結果、投薬情報などの患者情報をデジタルで一元管理できるシステムです。これにより、診療中の情報確認が迅速になり、複数の医師や部門間での情報共有が容易になります。また、自動入力やテンプレート機能によって入力業務が効率化され、医療従事者の負担軽減にもつながります。
さらに、他の医療機関や専門医との連携にも貢献し、過去の診療履歴を正確に把握したうえでの治療が可能となるなど、患者にとってもメリットがあります。セキュリティ面では、個人情報の漏えいを防ぐための厳格な対策が施されており、安全性の高い運用が可能です。
近年の診療報酬改定では、電子カルテの情報活用状況が評価対象となっております。そのため、今後は単なる記録手段ではなく、医療の質向上や経営改善の基盤として、さらに重要性を増すと考えられています。
医療情報取得加算の仕組みと運用上の注意点
医療情報取得加算は、オンライン資格確認システムなどを通じて患者の薬剤情報や特定健診情報、受診履歴などを取得します。その情報を診療に活用して高品質な医療提供体制が構築されている場合に、診療報酬として加算される制度です。ここでは、制度の概要および運用上の主な注意点について解説いたします。
医療情報取得加算の概要
制度の目的と背景
医療情報取得加算は、かつて「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」として運用されていた制度です。近年の診療報酬改定により名称が変更されました。
この制度は、オンライン資格確認システムを活用し、患者の診療情報を取得・活用できる体制を評価するものです。重複投薬の防止や適切な治療を可能とし、患者の安全性向上を目的としています。
初診・再診時の点数設定
加算点数は、マイナ保険証の利用有無や、他医療機関からの情報提供の有無によって変わります。
- 初診時:マイナ保険証未使用 → 3点
- 初診時:マイナ保険証使用 or 他院から情報提供あり → 1点
- 再診時(3か月に1回):マイナ保険証未使用 → 2点
- 再診時:マイナ保険証使用 or 他院から情報提供あり → 1点
再診時の加算は、3か月に1回に限定されるため、算定のタイミング管理が重要です。
施設基準と運用要件
医療情報取得加算を算定するには、以下の施設基準を満たす必要があります。
- 電子情報処理組織を使用して診療報酬請求を行っている
- オンライン資格確認を円滑に実施できる体制を有している
- 取得した診療情報を実際の診療に活用できる体制を整備している
- 上記体制の概要を院内や公式ウェブサイトなどに掲示している
運用上の注意点
説明と同意の徹底
医療情報取得加算を算定するためには、患者に対して診療情報を取得し活用する旨を事前に説明し、同意を得るプロセスが必須となります。医療従事者は、わかりやすい説明資料を用意し、患者が安心して同意できるよう努めることが重要です。
情報共有と連携の強化
初診時の加算では、他医療機関から提供された診療情報の有無も評価対象となります。したがって、医療機関間での情報共有ルートや連携体制を整備し、必要な診療情報が確実に反映されるようにすることが求められます。
データ管理およびセキュリティ対策
オンラインで取得した患者情報は、厳格に管理する必要があります。個人情報保護法に基づく適切なセキュリティ対策を講じるとともに、不正アクセス防止策や定期的なシステム監査を実施することが欠かせません。
診療タイミングの把握とシステム運用の見直し
再診時の加算は3か月に1回に限定されるため、同一患者に対する加算の重複計上を避けるための診療タイミングの管理が重要です。電子カルテやオンラインシステムと連携したデータ管理体制を整え、診療実績のモニタリングおよび分析を行うことで、より正確な算定が可能となります。
以上のように、医療情報取得加算は、オンライン資格確認システムの活用および診療情報の適切な運用を基盤として、医療機関の診療の質の向上を図る重要な制度です。医療現場では、最新の診療報酬改定に基づいた運用体制の構築と、電子カルテシステムとの連携を進めることで、患者に対してより安全で質の高い医療サービスを提供することが期待されます。
まとめ
電子カルテは、現代医療において情報の一元管理、業務効率の向上、さらには医療連携の促進といった多くのメリットがあります。そのため、各医療機関にとって不可欠なシステムとなっています。併せて、医療情報取得加算の改正により、オンライン資格確認システムを活用した診療情報の取得とその活用が、診療の質向上や患者安全の確保に直結する評価基準となりました。
今後も各医療機関が、電子カルテの効果的な運用とともに、医療情報取得加算の制度に基づいた適切な体制整備を進めることが求められます。