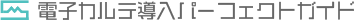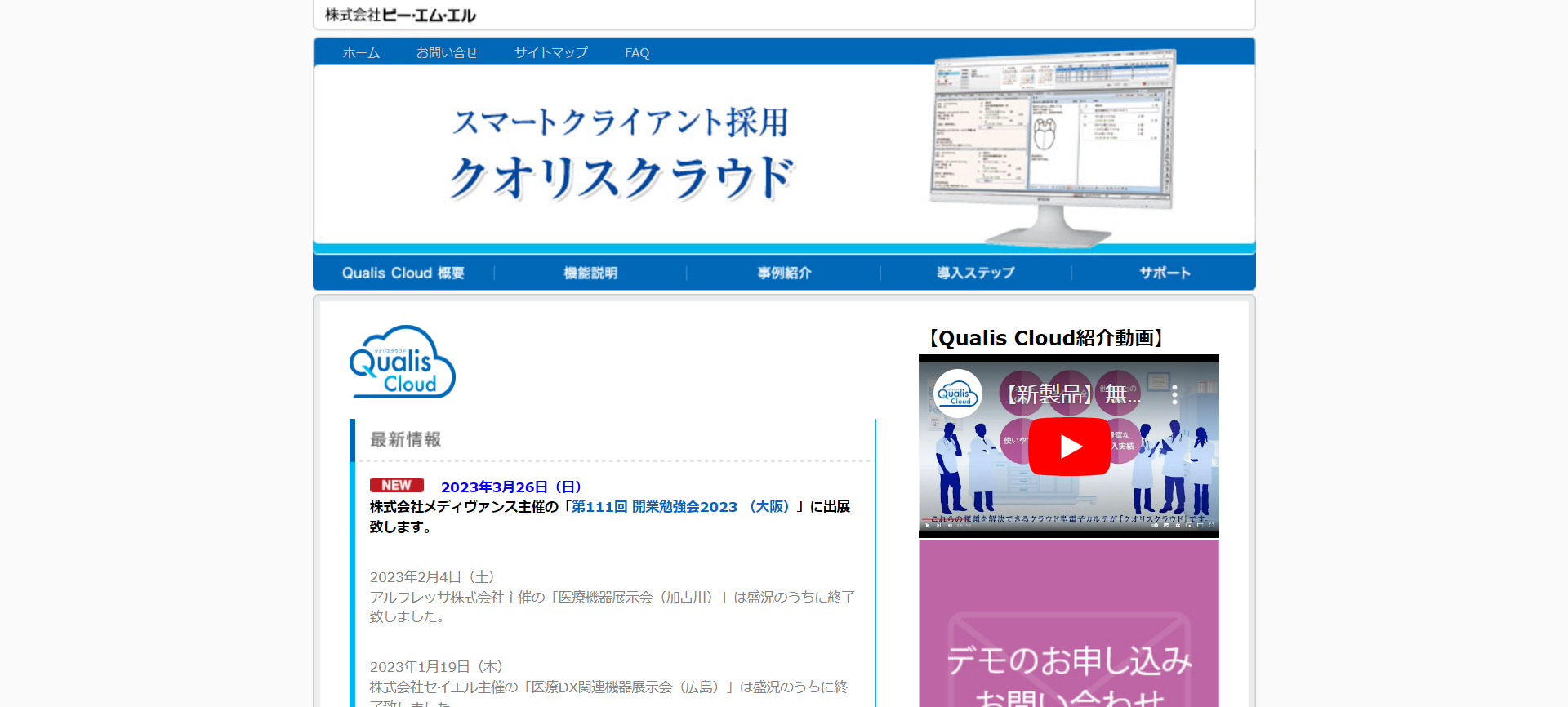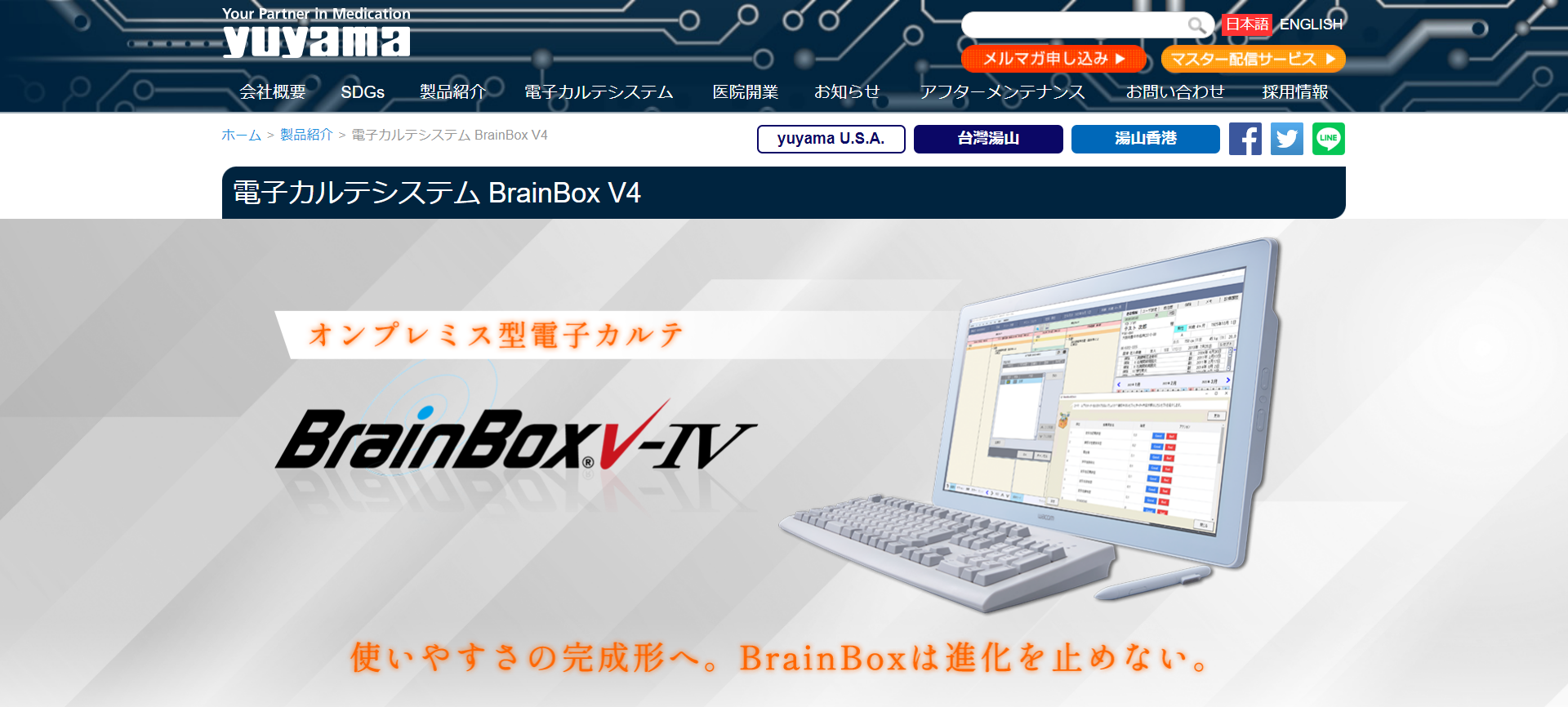電子カルテは義務化される?
電子カルテ義務化の背景と現状
高齢化が進む日本の医療現場では、より効率的で質の高い医療提供が求められています。そうした背景のもと、厚生労働省は「医療DX 令和ビジョン2030」を打ち出し、全国的な電子カルテ導入を推進しています。
この構想では、以下の3つの柱が掲げられています。
- 全国医療情報プラットフォームの創設
- 電子カルテ情報の標準化と普及
- 診療報酬改定DXの実現
2030年までに、全国の医療機関ほぼすべてに電子カルテを導入する方針です。2026年度までに普及率80%という目標も掲げられており、紙カルテからの移行は今後避けられない流れです。
現時点(2024年11月)では法的な義務ではないものの、今後の報酬制度や医療制度全体のデジタル化を見据えると、クリニックにとっても早期導入が賢明です。
電子カルテ導入のステップ
現状の把握とニーズ整理
まずは、院内の紙カルテ運用の課題を洗い出しましょう。保管スペースの問題や情報共有のしづらさ、転記ミスの発生などを整理し、「電子カルテで何を改善したいか」を明確にすることが重要です。
システム選定
次に、診療内容やスタッフのITスキルに合わせたシステムを選定します。選定時は以下の点に着目しましょう。
- 診療内容・クリニック規模に適した機能性
- 操作画面の見やすさ・使いやすさ
- セキュリティやサポート体制の充実度
- HL7 FHIRなどの標準規格への対応可否
複数のシステムでトライアル運用を行い、実際の業務で使いやすいかを検証するのがおすすめです。
導入準備と研修
システムが決まったら、必要なハードウェア(パソコン、サーバー等)やネットワークの準備を行います。紙カルテのデータ移行もこの段階で進めましょう。
スタッフ向けの研修も重要です。マニュアルの配布や説明会の開催などで、誰もがスムーズに使える体制を整えましょう。
試験運用
いきなり全体導入するのではなく、一部の診療業務や患者を対象に試験的に運用します。不具合や操作性の問題、セキュリティ面でのリスクを洗い出し、改善を加えながら本番運用に備えます。
本格運用と継続的改善
本稼働後も、スタッフの意見や患者からのフィードバックをもとに継続的な改善を行っていくことが大切です。システムベンダーとの連携も密に取りながら、診療の質向上に繋げていきましょう。
電子カルテ導入のメリットとデメリット
メリット
- 業務効率の大幅アップ:情報検索や文書作成がスピーディーに
- 医療ミスの低減:手書き誤読や転記ミスの防止
- 保管スペースの削減:デジタル保管で院内スペースを有効活用
- データ活用:将来的なAI・分析活用にも対応可能
デメリット
- 導入・運用コスト:初期費用と継続費用が必要
- システム障害リスク:停電・トラブル対策が必須
- スタッフのIT習熟:特に高齢スタッフの教育に時間がかかる
- セキュリティ対策:個人情報を守る体制づくりが不可欠
タイミングも気にしつつ導入を検討する
クリニックにとって電子カルテは、単なるデジタル化ではなく、医療の質を高めるための重要な基盤です。2030年までにほぼ全ての医療機関への導入が目標とされている今、早めの対応が大きなアドバンテージになります。
補助金を活用しつつ、スタッフ教育とワークフロー見直しを丁寧に行い、スムーズな移行を目指しましょう。政府が進める「標準型電子カルテ」の動向も注視しつつ、クリニックにとって適したタイミングでの導入を検討してみてください。